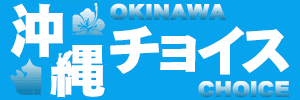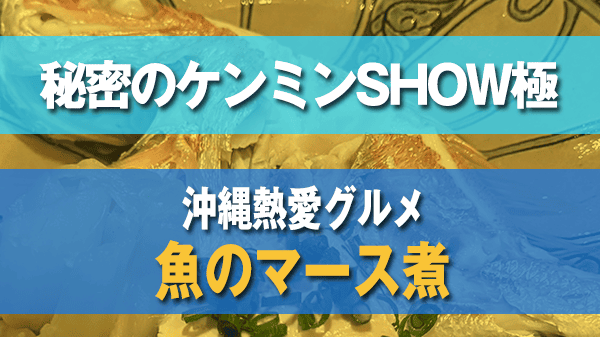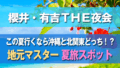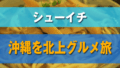2025年5月22日放送『秘密のケンミンSHOW極』では沖縄熱愛グルメとして「魚のマース煮」が紹介。沖縄県民が愛するマース(塩)だけで煮る魚の塩煮とは?
沖縄熱愛グルメ「魚のマース煮」
沖縄県で魚の煮物と言えば「マース煮」。マースとは沖縄の方言で塩のこと。
醤油煮や味噌煮よりマース煮が定番。
マース煮に使う魚
マース煮に使う魚は、
・マーエー(アイゴ)
・かりゆしキンメ(金目鯛)
・オーバチャー(ブダイの一種)
など、どれも白身魚。
塩オンリーの味付けはごまかしができない味付けで、魚から良い出汁が出る。
島豆腐を一緒に煮込むのは島豆腐は目が粗くて魚の出汁が染み込みやすいから。
島マース
魚のマース煮は沖縄の塩「島マース」で煮るからこそ引き出される魚本来の味と角の無い塩の甘さが最大の魅力。
一般的な食塩はほぼナトリウムで塩味が強いのに対し、ミネラルを豊富に含む島マースは塩味だけでなく甘味・酸味・旨み・苦味・雑味が感じられる。
塩オンリーのマース煮の作り方
1.深めのフライパンにウロコを処理した魚を丸々一匹と水を入れる
2.島マースを大さじ2杯ほど入れる
3.塩味強めの魚の出汁をまわしかけ、島豆腐を加えてさらに煮込む
沖縄県民は塩焼きを食べない・・・?
公設市場の魚のプロに伺ったところ、
「沖縄の魚は脂があまり入っていないので、ただ塩焼きするだけではパサパサするだけで美味しくない。」
とのこと。
また、
「マース煮にすると魚が自分が出した出汁自体を自分にまとわりつかせるのですごく美味しくなる。」
とのこと。
居酒屋のマース煮
沖縄の居酒屋で出てくるマース煮は、基本どの魚が出てくるか分からないガチャシステム。
日によって変わる新鮮な魚で調理するため、特定の魚をメニューに載せていないことが多いとのこと。
なぜ沖縄県民にマース煮が根付いたのか・・・?
琉球大学・理学部教授の竹村明洋さんによると、
「14世紀から19世紀の琉球王国時代にマース煮が家庭料理として最初にできた。
醤油や味噌が高価なものとして琉球王国時代にはなかった。
食材として使えるのが塩。それに加えてほとんどが白身の魚。
となるとマース煮という料理が発達した。」
*本記事に掲載されている情報は記事作成時点のもので、現在の情報と異なる場合があります